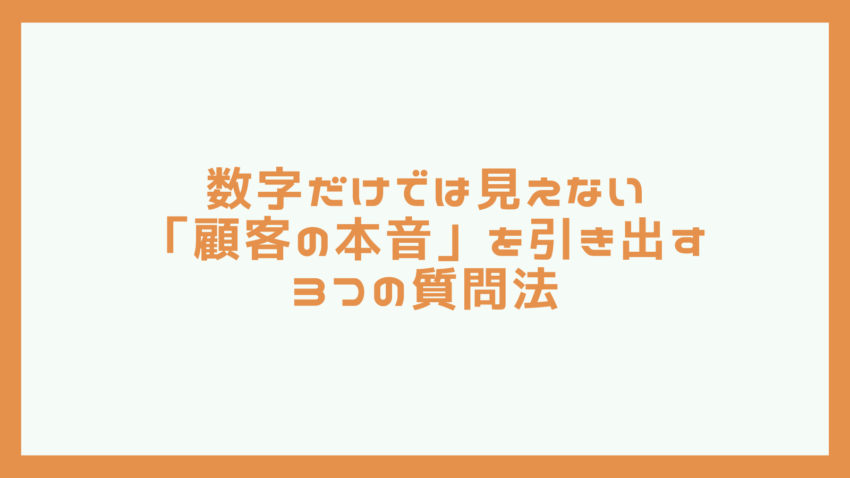顧客満足度が高いのにリピート率が低い理由とは?
先日、あるIT企業の社長からこんな言葉を聞きました。「顧客アンケートの満足度はいつも高評価なのに…なぜかリピート率が上がらないんです」。実はこれ、よくある話なんです。数値データでは見えない本質的な課題が隠れているケース。わたしが最近、インタビューしたある企業での出来事をお話ししましょう。
その会社も満足度は高かったのに継続率が伸び悩んでいました。ところが、顧客に具体的なエピソードを聞いていくと…「担当者の対応は良いけれど毎回同じ説明を聞かされる」という声が出てきたのです。これは、典型的な「見えない不満」でした。
顧客の本音を引き出す重要性
高評価の裏に隠れた顧客の本音を引き出すには、アンケートの数値だけではなく、具体的なエピソードに耳を傾けることが重要です。
数値データは客観的な満足度を示す指標として重要ですが、改善点を特定するための具体的な情報が不足しがちです。顧客は小さな不満があっても、全体的な評価では高評価をつけることが多く、本当の課題が見えづらくなります。具体的なエピソードを聞くことで、数字だけでは見えない改善点が明らかになります。
「見えない不満」を発見する3つの質問法
では、どうすれば「見えない不満」のような課題を発見できるのか。3つのポイントをご紹介します。
1. 具体的な場面を聞く
「いつ」「どこで」「何が」起きたのか、細かく掘り下げていきます。例えば「最近、私たちのサービスを使っていて印象に残った場面はありますか?」と質問し、具体的なシチュエーションを思い出してもらいます。
具体的な質問例:
- 「最後に弊社のサービスを利用されたとき、どんな状況でしたか?」
- 「サービス利用中に困ったことはありましたか?それはどんな場面でしたか?」
- 「特に印象に残っている担当者とのやり取りを教えていただけますか?」
2. 感情の変化を探る
そのとき、どんな気持ちを感じたのか、表情の変化も見逃さないようにします。「その時どう感じましたか?」と感情面に焦点を当てることで、表面的な回答を超えた本音を引き出せます。
具体的な質問例:
- 「その対応を受けたとき、どのような気持ちになりましたか?」
- 「何か不便さや違和感を感じた瞬間はありましたか?」
- 「もっとも満足感を得られた瞬間と、少し残念に思った瞬間を教えていただけますか?」
3. 理想の姿を描く
「どうなれば良かったか」まで聞くことで、改善のヒントが見えてくるでしょう。「もし理想的なサービスだったら、どうなっていると嬉しかったですか?」と尋ねることで、顧客が本当に求めている価値が明らかになります。
具体的な質問例:
- 「理想的なサービス体験とはどのようなものでしょうか?」
- 「もし1つだけ改善できるとしたら、何を変えてほしいですか?」
- 「他社で良いと感じたサービスや対応があれば教えてください」
実際の成功事例
実は最近、ある企業がこの方法で大きな成果を上げました。月に一度、ランダムに選んだ顧客5名に15分間のインタビューを実施したところ、「サポート対応は丁寧だが、毎回基本的な説明から始まるため時間がかかり過ぎる」という声が複数から上がりました。
そこで、顧客ごとに過去のやり取りを記録し、担当者間で共有するシステムを導入。さらに、熟練度に応じた対応マニュアルを作成して、リピーターには説明を省略するプロセスを確立しました。その結果、顧客の継続率が2倍に上がったのです。
数字ではなくエピソードに耳を傾ける
大切なのは、「数字」ではなく「エピソード」に耳を傾けること。満足度調査やNPS(顧客推奨度)などの数値は全体像を把握するのに役立ちますが、改善点を特定するには顧客の具体的な体験と感情に注目する必要があります。
あなたのビジネスでも実践してみませんか?
あなたのビジネスでも、顧客の「見えない不満」を発見し、サービスの質を向上させたいと思いませんか?わずか15分の会話から得られるインサイトが、リピート率を大きく改善する可能性を秘めています。顧客の本音を知ることで、競合との差別化にもつながるでしょう。
今日からできる簡単なステップ
まずは、直近の顧客3人に連絡して、15分程度の簡単なインタビューをお願いしてみましょう。「最近のサービス利用で印象に残った場面」「その時の感情」「理想の状態」という3つの質問を軸に会話を進めてください。得られた情報をもとに、すぐに改善できる点を一つでも見つけて実行してみましょう。小さな変化が、大きな成果につながるかもしれません。
インタビュー時のポイント
顧客インタビューを行う際は、批判的な意見も歓迎する姿勢を示すことが重要です。「改善点を教えていただくことが、私たちの成長につながります」と伝えると、本音を話しやすくなります。また、インタビュー後は必ずお礼を伝え、いただいた意見をどう活かすかを共有すると、顧客との信頼関係も深まります。